
葉山沖にて

太陽の照り付ける暑い中、今月も皆様ご参加いただきましてありがとうございます。
7月6日の例会参加者は72名(会員65名、ゲスト7名)。二次会の参加者は30名でした。
8月の例会はありません。9月の例会まで皆様心身ともにお健やかにお過ごしください。
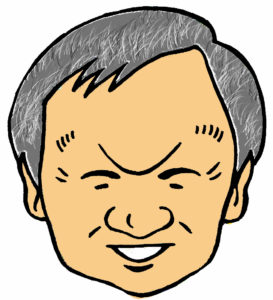
熊本会長
暑い中ご参加いただきありがとうございます。
皆さんNHKの大河ドラマ「べらぼう」を観ている方も多いと思いますが、先週の内容は浅間山の火山が噴火し天明の大噴火といわれ、その噴火の火山灰が江戸市中まで降り注ぐ激しいものでした。ここまでは先週の放送でした。
今週の放送内容の予想ですが、この噴火により農作物に大変な被害をもたらし、江戸ではコメの価格が高騰しコメ騒動が起き、その対策として田沼意次政権はコメの流通にかかわるのは株仲間に限定していましたが、だれでもコメの売り買いができるようにしました。しかしこれが裏目となり金持ちが買い占め、一層コメが高騰して田沼政権失脚の一因といわれています。今の日本のコメ不足と似ているようなところがありますね。
「歴史に学ぶ」と格言がありますが、今の政権は方向を誤れば失脚につながり「歴史は繰り返す」となります。このように考えて「べらぼう」を観ると興味深く見れるのではないでしょうか。少し長くなりましたが熱中症の予防のため水分を十分にとるようお願いして挨拶に代えさせて頂きます。

高橋正一さん・・・演題「内裏(天皇の住まい)と廷臣(公家達)の住まいの変遷 その2」
昨年に引き続き今回は戦国時代からの内裏と公家の住まいについての発表である。内裏の場所が固定され、その四方を取り囲むように公家町が形成される。公家の家格も固定される。(五摂家、清華家、大臣家、羽林家、名家、半家)平面図を見ると必ずしも家格と敷地面積、禄高が対応していないこともわかる。江戸時代の京都御苑や公家町のバーチャル映像は当時の様子が分かり、平面図と見比べるとイメージがわきやすい。明治天皇が東京に居住されると廷臣も東京に転居して公家町の荒廃が進むが、その後保存修理で現在の京都御苑の姿となった。冷泉家はその中でも京都に残る唯一の公家屋敷で冷泉家伝来の古書を納めていた土蔵(時雨亭文庫)は屋敷内でも神聖な場所とされ当主と嫡男以外は立ち入ることができない。今回発表者は特別に屋敷内で撮影した貴重な写真を映し出しながら説明された。一般公開時でも外観のみの見学となるので大変貴重な発表であった。

時間が来てしまい映像が途中で残念ですね。料亭の女将さんともお知り合いとはさすが高橋さんです。承久の乱で内裏が焼けてしまい、再建されるまで時間がかかりました。私も調べていますが平面図ではよくわからないが今回の映像でよくわかりました。
小川眞一さん・・・演題「鹿島神宮と鹿島の太刀」
日本の伝統文化に興味を持ち、毎月明治神宮の道場に通って合気道と剣術の稽古をしているという小川さんの武術についての初めての発表です。武術は東国に発するということで武神を祀る鹿島神宮の太刀や神話的背景、「鹿島の太刀」の剣豪や系譜、鹿島神宮と香取神宮の歴史・由緒、そして鹿島の太刀の術理・理念など多岐にわたる発表で一回だけの発表ではもったいない内容であった。「鹿島の太刀」は日本武術の源流であり神職たちによって展開してきた。鹿島・香取は海上・水上交通の要路であり、両神宮とも軍神として崇敬の深い神社であり、地勢学的重要地にある。そして礼儀作法、精神の鍛錬、自然との調和といった共通の価値観を持つ神道と武道の精神性、関係性についてまとめられた。

相手を尊重する気持ちでが大事ということですね。ボリュームのあるレジメです。今は増えましたが延喜式に載っている神宮というのは香取神宮、鹿島神宮と伊勢神宮の三社しかない。格の高い神宮というのがなぜ離れた茨木や千葉にあるのでしょうか。神武東征と関係があり、出雲制圧した二神が拠点とした(坂上田村麻呂も)特別な地で本殿は北を向き東北をにらんでいる。知らない話がたくさん出て、確か特攻隊もお参りに行かれました。機会があったら一度行かれてみてもよいでしょう。
長尾正和さん・・・演題「わが国古代国家の成り立ちと東国」
古代国家形成の歴史についての研究はこれまでは北九州や近畿など西の地域が主流だったが、考古学や文献史学の研究が進み東国勢力の関与も考えられてきている。弥生時代の大型集落や邪馬台国・卑弥呼、纏向遺跡や前方後円墳など大和王権にかかわる遺跡までを通して、東国については吉野ケ里遺跡に匹敵する大型の朝日遺跡があり、方形周溝墓や前方後方型の墳丘墓が出現。東海地域には前方後方墳が現れ、北陸、甲信、関東にも築造される。大和王権の前方後円墳とは異なる墳丘墓の勢力、ここで「卑弥呼に従わない狗奴国」とは東海勢力の尾張氏と考えられるのではと。大和政権の東国支配については東征といわれるが、屯倉や国造の設立など早くからおこなわれて戦ってはいないのではと思われる。豪族上野毛氏は牧の馬の生産で大きな力を持った。延喜式による国力の大きさでは東国が半数以上を占めている。以前発表された三英傑の信長、秀吉、家康も東国出身であると結び、今後の東国研究の展開が楽しみである。

長尾さんは古代史の発表になると、やはり熱が入り迫力のある発表でした。
最新の研究によって、ヤマト王権成立過程で東国・関東の豪族が大きく貢献していたことが良く分かりました。
【横歴勉強会】
***古文書講座のご案内***
会員の方に向けて古文書の勉強会を毎月1回、開催中です。
第6回古文書講座は7月27日(日)
第7回古文書講座は9月14日(日)
・・・・・午後2時~4時 横浜市歴史博物館・・・・・
*前回の配布資料をご持参ください。6月欠席された方には今回お渡しします。
*新規参加希望者は竹内副会長・金子理事、または各班長にお問い合わせください。
横歴会員の活動のお知らせ
***学童疎開の体験から***
講演者 田代 信太郎氏 8月5日(火)午前10時~11時
第一部 学童集団疎開についての講演
第二部 戦中戦後の横浜のこと、自分の体験や聞いた話などを参加者同士で語り合う座談会
会 場 横浜市南図書館 (参加無料 申し込み不要) 京浜急行弘明寺駅より徒歩1分
定 員 30人 (当日先着順、直接会場へ)