
「稲荷山古墳」
2025年5月横歴バスツア-にて

9月の残暑から抜け出し、10月に入り朝晩の涼しさにホッとしています。寒いくらいの日もあるので風邪ひきにはご注意ください。10月4日の例会参加者は74名(会員67名、ゲスト7名)二次会の参加者は33名でした。
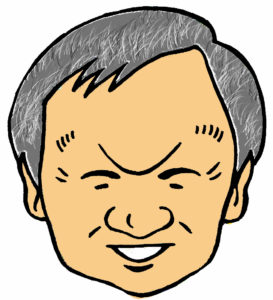
熊本会長
こんにちは、一雨ごとに寒くなってくるようです。明後日6日は中秋の名月ですが、当日の天気予報は曇りなので名月の鑑賞は無理かなと思います。本日総裁選挙が行われています。大河ドラマの中で積極財政は田沼意次、緊縮財政は松平定信です。歴史は繰り返されるという言葉もありますが、さてどうなるでしょう。、例会の終わるころには結果も出ているころだろうと思いますが最後まで発表を聞いていってください。最近インフルエンザが流行ってきています。10月1日から予防接種が行われています。治療もひどくなると大変ですので、予防接種などもしておいたほうが良いかなと思います。

上野 隆千さん・・・・・演題「公武の力関係を劇的に変えた承久の乱」

幅広い知識をお持ちの上野氏、今回は中世承久の乱についての発表です。文武両道であった後鳥羽院は三代将軍実朝と非常に良好な関係であったが実朝が暗殺されたのち親王の下向を撤回、亀菊への荘園の地頭改補の院宣を出す。この荘園問題は北条義時に対する瀬踏みではないか、後鳥羽院は実朝同様、義時をコントロールできるのか試したのではと。幕府内での権力闘争から内裏が焼失したが再建に非協力な義時に怒り、討幕ではなく北条氏から三浦氏への幕府の入れ替えを狙ったものであり、義時排除に動いたが幕府の迅速な動きに敗れた。。承久の乱の歴史的意義は鎌倉幕府の支配が東国から西国にも及ぶようになったこと、それ以降700年近く武家が主導権を握るようになったことである。まず最初に結果について語り、それに至った朝廷と幕府とのかかわりについて解説されるという手法を変えての発表であった。
(質)承久の乱後、北条義時が急死しています。毒殺が疑われていますが発表者はどう思いますか。泰村ではないかと言われたが奥さんか。
(応)奥さんが毒を盛ったのではないかともいわれています。非常に苦しんでなくなったことは間違いない。三浦泰村ではないかという話もあるが事実は分からない。北条泰時は非情であるが吾妻鏡では温情主義と良く書かれている。義時は吾妻鏡の中ではあまりよく書かれていない。
(質)承久の乱後に幕府の支配体制が52国の内26→38となっている、増えてはいるががなぜ全部にはならないのか。100にはならないのか。
(応)朝廷の支配体制から幕府の支配体制が増えているが中国・九州地方は入らない。独立していたりするので100にはならない。
江泉 良幸さん・・・・・演題「フランス革命」

今回が初めての発表となる江泉氏、非常に慣れ落ち着いて、聴衆の反応を計算しながらの熱のこもった発表となった。フランス革命がわずか3か月で封建制が崩壊した理由とその後の恐怖政治に陥った原因をわかりやすく解説された。身分制度、新税の導入、軍隊の動員、戦争による財政危機、国王の逃亡などから国民の信頼が揺らぎ不満が爆発した。さらに改革後の国内での党派の対立からロベスピエールによる恐怖政治への正当化など。税負担や国の歳入と歳出、政治勢力の変遷を表で表し、また随所にコラムなどを挟み込んで変化を持たせる発表であった。「ヴェルサイユのバラ」でコミックやアニメ宝塚などでも多くに周知されているフランス革命だが改めてわずかな期間で大きく変わった原因を再認識することができた。
(質)言葉の問題でよくわからないのがブルジョワジーの意味、昔よくブルジョワとか使っていたが時代の流れで意味が変わっていったのか。
(応)基本は商売人とか商売をやっている、お金を得ている人という意味。
(質)反発した主婦が・・、とあるがこの時代に主婦が(ブルジョワジーか農民の奥さんの主婦でしょうか)団体で活動したことがあるのか。
(応)主婦です。食料事情が背景にありました。「男はバスチーユで天下を取った。女はベルサイユ行進で・・・」という言葉がありました。
(質)ヨーロッパにはほかにも王政国家がありましたがなぜフランスだったのか。飢饉はほかの国でもあったのでは。
(応)フランスの支配階級は一枚岩ではない。政治構造がばらばらでイギリスなどは国王と他がもっとうまく付き合ってやっている。

この時、日本では松平定信が寛政の改革を行っていた。100年たってフランス革命を起点とした改革が始まった(日本に入ってきた)日本への影響は百年たってからで急進的なものはあまり望んでいなかった。知らないことが多くあり勉強になりました。
西沢 昭さん・・・・・演題「時代の流れと相鉄沿線映画館事情」

日本史や世界史の通史ではなく視点を変えて、その当時の常識変化から歴史観の再認識を試みる西沢氏の発表です。戦前戦後の相鉄沿線の街や映画館の状況、また、昭和20年代から30年代の映画館事情を当時の新聞記事を探し出し、映像娯楽が映画からテレビに大きく変わった様子をデータにまとめ検証した。映画館が作られた地域や入場者数などから地域の特性や発展も分かり、33年をピークに激減していった。映画館の経営者や支配人の移り変わりなどのデータから映像娯楽が映画館や役者の起用から、今は形を変えてデジタルや配信へと移行していっていることも推測される。発表に使用された新聞記事は毎日図書館に通って過去の新聞をめくりながら探し続けたという。昭和33年の神奈川新聞の記事や希望が丘高校新聞など、その根気と努力には頭が下がる。歴史研究と一口に言っても視点を変えることでこんなに面白い発見があるということに気づかされ、大変興味深い発表であった。
(質)映画は最初活動写真と言われ、無声映画で講談師がやっていたが、活動写真が映画に代わった時期は。
(応)調べていないが映画館ができたのが大正時代の終わりごろから昭和の初めにかけてなのでそのころ変わったのでは。それまではもっと小さなところでやっていた活動写真では。
(質)販売ルートを増やして映画の売り上げは変わっていないがスターの収入は増えているのか、減っているのではないか。
(応)結論は分からないので?を付けている。スターの収入は昔も今も変わらないのでは。細かくは調べていない。
(質)映画が作られた本数は平成27年547本、今はもっと増えている。『国宝』や「鬼滅の刃」などヒットしている。映画館は減っているのに映画数は増えている、どこでやっているのか。
(応)役者が動く映画はお金がかかってもうからない。映画館だけでなく飛行機やメディア、ネットで放映されているのではと推測されます。
(質)映画館はいらない、デジタルの時代で制作費が安くできる。昔は人海戦術でやっていたが今はだれでもデジタルでできるので昔我々が見ていた時代のものとは違う。

昭和40年ごろ夏の暑いときはオールナイトで座頭市などを見て涼んだ。高校時代は映画禁止でした。新聞記事が色々あるが・・。
(演者)昭和35年ごろの八戸では9本立て80円でした。図書館で新聞一枚ずつめくりながら自分で探した。